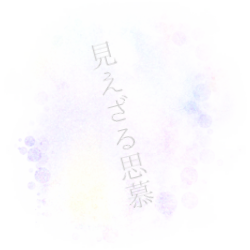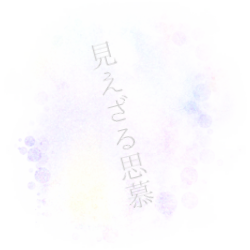酒の席で一人片隅に座る女がいることに気がついたのは少し前のことだ。
よくよく見れば食事はしっかり食べているが酒には殆ど口をつけていない。話を振られない限り喋らない静かな女の名前はだと三成から聞いたことがある。
名前を知り得たはいいが話す機会が一向に訪れない。は大勢いる武将の中の一人であり、吉継自身もその内の一人であるのに今まで話す機会がなかったのが不思議なほどだ。
賑やかになって皆が席を自由に移動する頃になると、たまにはこの場からそっと抜け出すことがあった。気配を消すのが上手いなと吉継が感心したのは、初めて彼女が抜け出したのを見た日のことだ。
誰もを引きとめない。と言うより彼女が部屋を抜け出したことに気づいていないのだ。それほどに皆酔いが回って細かいところまで気が回らなくなっている。
自然と目でを追っていた吉継の視線に彼女は気づくことはなかった。
ある日の盛大な宴でまたはそっと立ち上がって部屋を出た。吉継は少し考え、のそりと立ち上がり、興味本位で後をつけた。彼もまた気配を消して部屋を抜け出すことに長けた人物であった。
自分の少し先をが歩き、吉継は背後霊のようにその後を追った。我ながら驚くほど足音が立たないと思う。おかげでと言うべきか、は一度も振り返らなかった。
は人気がない廊下まで来ると縁側に腰を下ろして曇った空を見上げた。月が雲に隠れているので辺りは真っ暗だ。そんな中にぬうっと白い姿が浮かび上がると、いくら戦場を駆け回る武将と言えど悲鳴を上げるのは必至だ。
「すまない。驚かせてしまったか」
激しく鳴る心臓を抑えるように胸に手を当てたは首を横に振った。吉継が喋ったことより、今まで感じられなかった気配が突然現れたことに驚いて動揺した。本気で幽霊かと思ってしまった。
そうか、と言って納得した吉継はそれだけ言って何か喋るでもなくこの場から立ち去ろうともしない。暫しの逡巡の後、は恐る恐る尋ねた。
「ど、どうしてこんなところに?」
「……酔いを醒ますためだ」
咄嗟に考えた嘘だった。ほんの少しの好奇心だけが吉継を動かしたので、後を追いかけた目的を明確にしていなかったのだ。
訝しげな視線を吉継に送ったは何か言おうと口を開いたが、その機を逃さず吉継は名前は何だったかと恍けたように訊ねた。なるべく自然な形で会話に持ち込もうとするために敢えて訊ねたのだ。
それから吉継はごく自然な動作での隣に腰を下ろした。
「お前は何故抜け出したんだ?」
「酒はどうも駄目で……あと、ああいう場は緊張してしまって」
「しかし秀吉様に招待されたのだろう」
「はい。ですが少し酔いが回ってしまったので、部屋を出る前に外の空気を吸いに行く許可をいただきました」
「秀吉様にか?」
「いえ、三成殿に」
暗がりのせいで顔色までは分からないが、つまり今は気分が優れないということなのだろう。聞けば「ここで吐かれても迷惑極まりない。さっさとその覇気のない顔をどうにかして来い」と三成に言われたらしい。いかにも彼らしい言い回しに吉継は布の下で苦笑した。
酒に殆ど口をつけないのは苦手だから。しかし秀吉が飲めと言えば飲まなくてはいけないし、目の前で勧められてしまえば断れるはずもない。つくづくそんな己が嫌らしいはため息を吐いた。
「酒も人と話すことも苦手なので、賑やかな宴の席では居たたまれなくなってしまいます」
「俺とは今、普通に話せているだろう」
「そ、そうでしょうか。あまり得意ではないので自分ではよく分かりません」
「別段おかしなところはない」
「それなら良いのですが」
確かにそうなのかもしれないと吉継が感じた理由は、があまりこちらを見ないからだ。隣に並んで座っているのだから一々顔を見て喋らなくても困ることはないが、月明りしかないこの廊下では横から見たの表情の変化がよく見えない。
会話が得意かそうではないかを考えたことはなかった。吉継も口数は少ない方だが人との会話が嫌いなわけではない。
しかしせっかくと話す機会を得たのだから色々な話をしてみたいのに、いざその時が来た今は案外気の利いた言葉が思い浮かばない。
思案に耽っていると、先にが恐る恐る話しかけて来た。
「あの、大谷殿」
「何だ?」
「戻らなくても大丈夫ですか?」
「何故だ?」
「な、何故って……」
「邪魔なようなら戻るが」
「えっ、いや!そんなことはありません!」
吉継の答えは自分の期待するものとは全く違うものだったらしい。は顔を上げて慌てて否定した。
ようやく顔を上げてくれたことを喜ぶべきかもしれない。わたわたとしているの様子を見ていると何故だかそう思えて、吉継は無意識のうちに目を細めた。
「すみません、言葉足らずで……大谷殿ほどの方があの場に居られないのでは周りの方々が心配されるでしょう」
「それはお前にも言えることではないのか?」
「いや、そんな。私はただの一兵卒に過ぎません。むしろ宴に呼ばれたことが不思議なくらいです」
随分と謙遜するのには理由がある。武家の中でも比較的貧しい家の出であるにとっては、絢爛豪華な城や宴は眩しすぎるのだ。
似たような出身の友がいる吉継はその男とを比べた。似ても似つかない性格であることが不思議でならない。
やはりの酔いは覚めていないのだろうか。それともまだ酔いが抜けないのだろうか。普段の彼女がどのように話すのか、どんな表情を他人に向けるのか吉継は知らないのだ。
宴でのの振る舞いや彼女の口ぶりからして、こんな風に進んで自分のことを誰かに打ち明けるような性格には思えない。もしもこれが酔いのせいだとしたら素面でいた時は避けられてしまうかも、という予感がした。同時に寂しさが吉継に芽生える。
「……お前は少々、自分を卑下し過ぎるきらいがあるな」
「そうかもしれません。それに、少しお喋りが過ぎた気がします」
「酔いのせいか?」
「いえ、あの……抜け出したのは実は、酒のせいではないんです。確かに酒は苦手ですが、今日ばかりは宴の場に呑まれたと言うか何と言うか」
「なるほど。人や雰囲気に酔ったということか」
「み、三成殿には何卒ご内密に……」
親にいたずらがばれるのを恐れる子どものような懇願だった。秀吉にではなく三成にというところがミソである。
宴に呼ぶくらいなのだからはそれなりに武勇の腕は立つのだろうし、何より秀吉が気にかけてくれているのなら彼のお気に入りであることに違いない。
思い返してみれば三成の口からの名前が出た時、彼は決まって文句を並べていたような気がする。の素行をどうこう言う様はまるで親兄弟のようだった。仲がいいのかと思ったが二人の間には見えない上下関係があるらしい。三成に小言を言われて縮こまるの様子が容易に想像できる。
「さて、どうしようかな」
淡々としているが吉継の口調はどことなく楽しそうだった。もちろん三成に告げ口なんてするつもりはないのだが、の表情がころころと変わるのでほんの少しからかってみたくなったのだ。
にしてみれば表情の読めない吉継のそんな気持ちなど伝わるはずがなかった。初めて話した女と懇意にしている友ならば確実に後者に味方するだろう。表情が全く変わらない吉継を見ては困ったように更に眉尻を下げた。
冗談が通じないのか真面目なのか、そういうところは三成に似ている気がする。ふっと笑うとは不思議そうに首を傾げた。
「冗談だ。そんなに泣きそうな顔をするな」
「そんなつもりは……そういう顔でしたか?」
「ああ。三成が怖いのか?」
「怖いというか、躾に厳しかった母を思い出します」
「父親ではなく母親か。三成に聞かせてやりたいものだ」
「……それも、内緒でお願いします」
見かけに似合わずおどけたことを言う吉継に安堵したのか、少しだけの表情が和らいだ。それでもまだ恥ずかしそうにしているのは吉継に打ち明けた秘密が幼稚な気がしたからだ。
初めて話した相手にみっともない姿を晒してしまった。けれど吉継の纏う独特な雰囲気のせいでうっかり口を滑らせてしまったような気もする。いやそれともやはり酔いのせいか。の頭の中でそんな言い訳が堂々巡りをしている。
そんな彼女の一喜一憂を眺めていると、ふと妙案が吉継に降臨した。
「そうだな。三成に黙っている代わりに、もう少しここで俺に付き合って欲しい」
「それは構いませんが、私が話し相手でよろしいのですか?」
「俺はお前と話してみたかった」
あまりにも吉継が淡々と言うので、彼の表情が読めないこともあり社交辞令だろうかと思ったは目を見張った。布の舌では一体どんな表情を浮かべているのだろう。
しかしそこにどのような意図があろうと、そしてがそれに気づかなくとも、つまらない人間であると自覚していた自分にとって、どういうわけか吉継の言葉は胸をぎゅうっと締め付けた。