好ましく思っている相手なのに避けてしまう。どうするべきかと悩む間、頭に浮かんで胸を締め付けるのは、特別な思い出よりも日常の小さな幸だった。
余所余所しくで呼ぶのではなく、親しみを込めて名前で呼ぶようになるまでにはそこそこ時間がかかった。姿を見かければ声をかけることもあった。全体的に白いから目立つと言えば、不思議そうに首を傾げる姿が可愛らしかった。夜に薄暗い廊下で顔を合わせるよりも、明るい日の下で会う方が好きだった。
きっと吉継も気づいているだろう。何事も流れに乗ろうとする彼のことだから、何かを察して自分に近づいて来なくなるかもしれない。できれば今はそうしてほしいのだが、本当にそれでいいのだろうかとの頭を悩ませる日が続いた。
しかし悩んだ甲斐なく、の考えはことごとく外れた。が思うほど吉継は何にでも流されるだけの人間ではないし、物事に頓着しないわけでもない。豊臣に来てからの大きな変化だ。
そんな中で花見をしようという秀吉の急な誘いは吉継にとっては好都合だった。予想通りと言うべきか、その日の宴の席でも相変わらずは酒のせいで赤いのか青いのかよく分からない顔色をしていた。
吉継は離れた席でとねねが話しているのを見つめている。何を話しているのか、二人の表情を見れば大体分かる。一方、に酒を勧めた張本人である秀吉は、その少し離れたところで酔って楽しそうに笑っていた。
「吉継、どうした?」
「いや……桜を見ていただけだ」
「お前の視線の先には酔っぱらった馬鹿しかいないが」
「おい頭デッカチ!馬鹿って誰のことだよ!」
吉継の隣にいた三成だけがいつもと違う友の様子を訝し気に見ていた。ちょうど良い場所に正則がいた上に三成の声がそこまで届いてしまった。
元来勘の鋭い男である三成だが、上手い具合に勘違いをしてくれた。馬鹿と呼ばれた正則はずかずかと三成の目の前へやって来て文句を言っているが、若干呂律が回っていない。
そこへ更に出来上がった秀吉がやって来たので、吉継の視界も思考も遮られた。花見はまだまだ終わりそうにないどころか、遅くまで続くかもしれない。
気分良さそうに千鳥足で子飼い達の席へ歩いて行く秀吉の背中を見て「まったくもう」と、ねねが呆れた声を出した。
「、大丈夫?うちの人がごめんね」
「これくらい大丈夫ですよ。気を遣わせてすみません……あ、でも一応お水をいただいて来ます」
「あたしがもらって来ようか?」
「いやそんな、歩いた方が頭も冴えると思いますから。ちょっと行ってきますね」
ねねにそんなことをさせるわけにはいかないし、料理やら酒やらを忙しなく運ぶ侍女達を呼び止めるのも何だか申し訳ない。心配をしてくれたねねに礼を言って立ち上がったは、笑い声のする宴の場から遠ざかった。
歩いていると時々どっと笑う声が聞こえる。大勢が参加しているせいか、大分歩いて離れた場所にいても声が届いた。
水飲み場に到着して水を汲んで少しずつ飲み、時間をかけて一杯を飲み干して大きく息を吐いた。もう少し休んでから戻ろうと、再び水を汲みもう一杯飲んでいる時だった。
「」
「よっ……!ごほっ」
「大丈夫か?」
名前を呼ばれて振り返った先には吉継が立っていた。盛大に水を吹き出して咳き込むの背を撫でてくれた。かぶりを降って大丈夫だと示したが、いきなり現れた吉継を見て僅かに残っていた酔いも一瞬で覚めた。神出鬼没なのはいつものことだが、いつも以上に心の準備ができていなかった。
吹き出してしまった水が小袖の合わせを濡らしてしまった。すまない、と謝った吉継は、あの日初めて話した時と同じく淡々としていて、けれどもあの日とは違って眉尻が下がっているように見える。烏帽子と布で表情は見えはしないが。
「こちらこそ、はしたなくてすみません……ええと、どうしてここに?」
「こういう場でないと俺と話してはくれないだろう」
「そんなことは……」
「ある」
きっぱりと言い切ったのでそれ以上何も返せなくなってしまった。実際その通りである。
今までは一緒にいて居心地が良かった。けれど今の吉継の雰囲気は少し苦手だ。冷静なようでいて、その裏には何やら熱いものを感じる。彼に限らず、はこういう雰囲気になるといつも根負けしてしまう。三成がいい例である。
暗に理由を話してくれと言われているのだと思い、吉継の様子を伺うように訊ねた。
「もしかして吉継殿、噂は聞き及んでおりませんか?」
「噂?」
「……いえ、ご存じないままがいいと思います。どうかお気になさいませんように」
「そう言われてしまうと気になるのだが」
確かにそうですよね、といつもなら笑って返せたはずなのに、噂が噂だけに躊躇ってしまう。そもそもその噂こそ、が吉継を避けていた理由なのだ。知られてしまったらどうしようと悩んで逃げた結果がこれだ。
四方を塞がれているわけではないが逃してくれる気配が全くない。吉継を薙ぎ倒して行くわけにもいかず、観念しては重たい口を開いた。
「わ、私と吉継殿が、逢引していると」
言うのが恥ずかしくて仕方がない。どんな反応をされるのか怖くて吉継を見ることができなかった。噂の渦中にある相手にそれを直接伝えるなんて新手の拷問としか思えない。
それは勘弁願いたいな、なんて言われたら流石に泣くかもしれない。自分から避けておきながら都合が良すぎるだろうか。
今すぐ逃げ出したい衝動に駆られたが足が動かない。吉継も何も言わない。二人共微動だにせず黙したままでいると明るい声が飛び込んできた。
「ー?いる?」
「わっ!びっくりした……おねね様」
「あれ、吉継もいるね。お水は飲んだ?お団子があるから早くおいで!早くしないと正則達に食べられちゃうよ」
「い、今行きます!」
まさに助け舟だ。ねねを見た途端に地面に張り付いていた足がやっと動いたので、はすぐに外へ飛び出して行った。
振り返るのが怖かったが後ろに吉継の気配は感じられなかった。これで良かった、直接言って良かったのだ。しかし自分に言い聞かせたその言葉は、悩んでいた時よりもひどく自身を暗い気持ちにさせた。
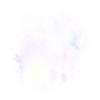
ねねが配慮してくれたおかげでは気分良く宴の終わりを迎えた。茶菓子を勧めてくれたので必要以上に酒を飲まずに済んだ。おかげて足元がふらつかずに屋敷に戻れそうだ。
一人また一人と帰って行く中、さわさわと心地よい風に舞う桜の花びらに見惚れた。宴の賑やかさの下で、という理由に加え、昼間のごたごたした件で気重であったので花を愛でる余裕がなかったのだ。
どうせなら夜桜を見て帰りたい。と同じことを考えている豊臣家臣は他にもいるようだ。各々談笑したり腰掛けたりして、先程の宴とは打って変わってこの場が静かで風情のある景色になりつつある。
「吉継殿……」
桜並木を眺めたり散る花びらを目で追ったり、一人で宛てもなく歩いてみようとふわふわした気分で桜並木へ足を踏み入れようとした。そんな時に吉継が現れたのだが今度は昼間ほど驚きはしなかった。だからと言ってが観念したわけではなく、思わず後ずさりしてしまった。
「おいで」
「え?うわっ、あの!ど、どこへ行くんですか?」
「そうだな……考え中だ」
不意に近づいて来たかと思えば片手を取られて何処かへ歩いて行く。いつも明確な答えをくれる吉継にしては珍しくはっきりしない答えだった。
桜並木を歩いても景観を楽しむ余裕はない。何か声をかけるべきかと思ったが、ただならぬ空気のせいでそれは叶わなかった。手は繋いだままで、痛くはないが吉継の爪がの手に食い込んでいる。少し力を入れて抵抗したくらいでは離してくれないだろう。手を握りしめる力はもちろん、見えない何かが吉継を突き動かしているように思えてならない。
どれくらい歩いたのか感覚が分からなくなった頃、次第に歩く速さが緩やかになる。歩みを止めてから握られた手がようやく離された。手の温もりが離れていくと肌寒い風が二人の手を撫でた。
「歩いている間に何から話すべきか考えていたが、考えがまとまらなかった。だが、お前の考えていることは予想がつく」
「な、何のことか……」
「俺達が夜に会っていたのを見て、噂好きの誰かがそのまた違う噂好きに面白おかしく話したのだろう」
何も密会よろしく夜にばかり会っていたわけではなかったが、そういう風に見られてもおかしくない理由に吉継は心当たりがあった。
がそれに気づいていたらこんな風に避けられることもなかったのだろうか。しかし彼女の性格を考えるとその可能性は低い。それにこういう流れに持って行ったのは他ならぬ吉継だ。
「恐らくだが原因は俺にある」
「どうしてですか?」
「お前は気がつかなかったようだが、俺は徐々に距離を詰めていたんだ」
「距離?」
それが物理的な距離という意味だとすぐに気がついた。現に今、二人の距離は初めの頃よりもずっと近い。前はと吉継の間に一人分の空間があったが、知らないうちにそれが埋められてしまった。
周りには誰もいないし今だけは噂を心配しなくていいのかもと安心した途端、吉継の言葉を意識してしまいの顔が紅潮していく。
逃げるつもりも後ずさるつもりもなかったのだが、言葉の衝撃によろめいたところで再びの手を吉継が捕らえた。握った後はそのままで、彼の目は逃げないで欲しいと訴えているように見えた。
「本来の思惑とは違う流れになってしまった。すまない」
「思惑、ですか」
「ああ。どうやら逢瀬を重ねていたと思っていたのは俺だけだったようだからな」
いつもながら吉継は恥ずかしげもなくの胸を奮わせるようなことをすらすらと言う。握られた手に力が込められて余計に意識してしまった。
年若い男女が頻繁に会っていればそう思えてくるのは仕方がない。噂が耳に届く頃、もしかするとその前には既に分かっていたのかもしれない。しかし好ましいという感情が友人としてなのかその他のものであるのか、やっと理解したのはつい今しがただ。
逃げては駄目、直接言わなければ。握られた手をぎゅっと握り返すと僅かに吉継が反応した。
「あの、決して嫌だから避けていたのではないんです」
「ああ」
「迷惑かもしれないと悪い方向に考えてしまって」
「そうか」
「ほとぼりが冷めるまで大人しくしていようと……よ、吉継殿、聞いていますか?」
何故かぼんやりしている吉継を心配そうに見上げた。当の本人はが必死に主張するのが面白くて、つい空返事をしてしまっただけだった。「分かっている」と一言、今までと同じような優しい声がの心を満たしてくれた。
安堵したのか、はにかんだは露の零れるような目をしている。それを見て庇護欲なのか加虐心なのかよく分からないざわざわとした感情が吉継に芽生えたが、表情を読み取られないのが幸いだった。寸でのところで手を伸ばしそうになるのを抑え、その代わりに胸の内を吐露した。
「てっきり嫌われてしまったのかと思っていた」
「嫌いだなんてとんでもない!……」
やや強い風が吹いて桜の花びらが舞い散る。お互いの髪が風になびいて花が散らしてあるように美しく映えた。
風の音でが後半に何を言ったのか聞き取れなかった。聞き返しても良かったのだが、ほんのり赤く染まったの顔を見ると、先ほど抑えたばかりのものが再び顔を出した。もう答えがなくても構わない。
が風で揺れる自身の髪を抑えると、辺りはもう日が沈みそうで薄暗いのに、急に視界が雪のような白が覆った。春の夜の肌寒さは何処へやら、体を包む温かさに気がついたのはすぐ近くで吉継の息づかいを感じてからだ。
我に返るまで時間かはかからなかったが、情けない声が出てしまった。たまに吉継は唐突な行動をとるから心の準備をする間もなく驚かされてしまう。
「よ、吉継殿」
「嫌なら思い切り突き飛ばしてくれ」
そう言うくせに力加減はしてくれない。が身じろぐ度にそれを抑え込もうとしているのだ。締められても苦しくはないが、驚きやら緊張やらで息ができなくなっていく。
いつもなら慌てふためいてしまうだろうに、この状況下で焦っているのはではなくむしろ吉継の方なのだろう。だからなのか、不思議なくらいは冷静になっていく。吉継の言動が矛盾しているせいかもしれない。
「何と言いますか、そういう流れというものなんでしょうか?」
「どうかな……そうだといいが」
「それなら、流れに乗らないわけにはいきませんね」
そうは言ったものの行動に移すとなると勇気が要る。控えめに吉継の背に手を伸ばして胸に頬を寄せることが今のの限界だった。こちらも力を込めて抱きしめ返すべきなのかも、他に何か正解があるのかも、と行動に移した後で考えてしまったが今更だ。
けれども今まで必死に逃さないように抱きしめていた吉継の腕からゆるゆると力が抜けていった。
思慕の情が高ぶっているのは最早一人だけではない。今度はの温かさを確かめるように優しくしっかりと掻き抱いた。